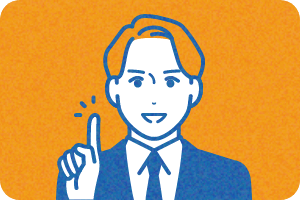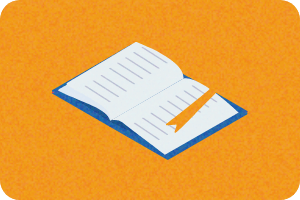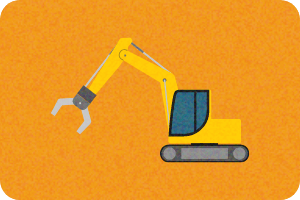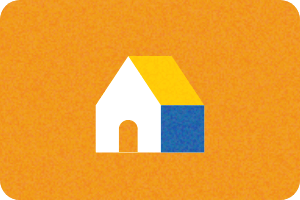お知らせ・コラム
お役立ちコラム
解体工事は許可なしでもできる?罰則や注意点

解体工事を行っている業者のなかには、無資格で業務を行ってしまうケースもあります。
無許可で解体工事を行うと重い罰則がありますし、依頼した施主側が気を付けなくてはいけない許可もあります。初めて解体工事を依頼する人のなかには「必要な許可がわかりにくい」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
解体工事を無許可で行った場合の罰則や注意点など、 覚えておきたいポイント について詳しく説明します。
無許可の解体工事は罰則の対象になる

「解体工事業登録」は、500万円未満の解体工事を請け負っている業者の取得が義務付けられています。そのため、中小規模の解体業者が取得している資格になり、ブロック塀の解体など部分的な解体を行う業者が対象です。
解体工事業登録を受けずに解体工事を営むと、罰則適用対象となり”1年以下の懲役または50万円以下の罰金”となります。また、500万円以上の解体工事になると「建設業許可」が必要になってきます。
坪数の大きな家を解体するときや、建物以外にも残置物やアスベストなど追加費用がかかり、500万円以上になってしまうケースもあります。
業者のなかには、当初はそこまで大きな解体は行っていなかったものの、
次第に規模が大きくなることで許可を取らずに請け負っていたという場合もあります。
また、解体工事中に出た廃材を収集したり運搬するのに必要な「産業廃棄物収集運搬業許可」や処理場で廃材を処分する業者に義務付けられた「産業廃棄物処分業許可」などもあります。これらの資格は、委託関係がなく自社で廃材を直接運搬するときは取得していないケースもあります。
解体業者がどのように廃棄物を処分するのか、必要な資格を持っているのか、 公式ホームページもしくは直接確認 しておきましょう。
施主側が必要になる資格とは

解体工事を行ううえで、施主側で申請しなくてはいけない許可もあります。
もし、手続きを忘れてしまうと重い罰則の対象になるため確認しておきましょう。
例えば、解体する建物にアスベストを使っている場合は、事前に「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出しておく必要があります。とはいえ、すべてのアスベスト除去に必要になるものではなく、人体に影響がでそうな場合にのみ義務付けられています。もし、申請をしないと10万円以下の罰金の対象となってしまいます。
他にも「建設リサイクル法に関する許可」は、事前に届け出が必要になります。床面積80平方メートル以上の建築物が対象となり、一般的な戸建てでも100平方メートルを超えるため許可を取る対象となります。
施主側が必要になる許可は、自分たちでは難しい場合解体業者に依頼できる場合もあります。手続きが不安なときは 事前に相談 してみるのもおすすめです。
無許可業者を利用しないための見極め方

無許可の解体業者に当たってしまうと、 トラブルの原因 となってしまいます。
そのため、無許可業者にあたらないためのチェックポイントを紹介します。
・ 見積書のなかに廃棄物処理費が無料になっていないか確認する
・ 解体業者のなかに必要な許可を取得している記載があるか見る
・ 国土交通省が運営しているホームページで情報を確認する
少しでもおかしいなと思う点があれば、確認するのをおすすめします。
また、質問した時の対応も含め、信頼できる業者かどうか見極めましょう。
まとめ
解体工事には、業者側と施主に必要な許可が変わってきます。
そのため、許可を取らずに解体を進めてしまうと、後々大きなトラブルになってしまうことがあります。
まずは、適切な許可を持っているかどうか、必要な許可のサポートをしてくれるか確認しておきましょう。